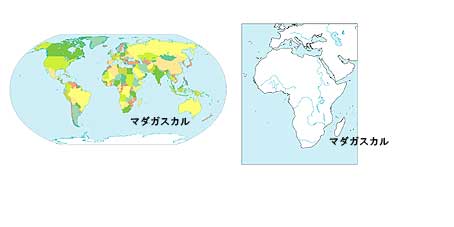
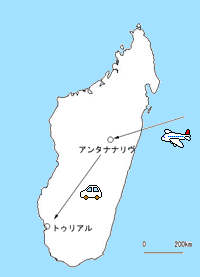
はじめに
マダガスカル・・・この国は化石、特にアンモナイトに興味を持っている人にはあこがれの場所の一つでしょう。
真珠色の殻の残った、
とてもきれいなアンモナイトの数々を最近目にする機会も増えました。
なかには一見”オパ−ル?”と見まちがうほど赤やグリ−ンに光り輝くものもあり、これらのアンモナイトは
マダガスカルという国の持つどこか神秘的な雰囲気
と実によくマッチしているように思います。
今回私は、これらのきれいなアンモナイトが掘り出されているところをこの目で直接見てみたい!、 そしてできたら実際にこの手で掘ってみたい!! という 単純な一心で、往復30時間かけマダガスカルまで行ってきました。
今回は特に
1)どこで掘っているか
2)だれが掘っているか
3)どのように掘っているか
4)そして何が掘れるのか
に焦点を当ててみました
。
1)どこで
マダガスカルの玄関口アンタナナリヴへは、去年の春開設されたばかりのバンコク経由の路線で入りました。
アンタナナリヴからトゥリアルまでは車で12時間あまりの長い長い道のりでした。
目的地は
トゥリアルの北東100kmのところにあります。
一番近い村からは車と歩きで4〜5時間かかります。
途中、道なき道を4WDで走り(幅20mほどの川を車で渡る)、その後炎天下の砂漠地帯を徒歩で行きました。
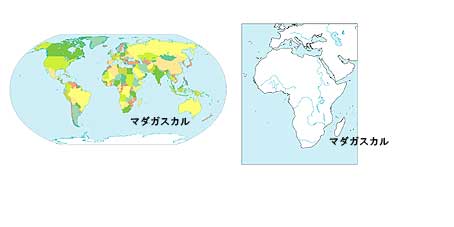 |
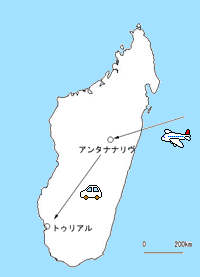 |
マダガスカルの位置 |
マダガスカルの地図 |
 |
 |
発掘地に行く途中の村で (電気もガスも水道もない) |
始めて見る日本人(東洋人)に興味津々集まってきた |
 |
 |
 |
| サファイアを採掘するため、掘り返された赤茶色の土地。 赤い土の元になっているのは粘土状の赤鉄鉱(酸化鉄の鉱物) | 直径1mほどのサファイアを掘っている穴 | 少し離れた町にあるサファイアを買い取る所(町中に何軒もある) |
アンモナイト発掘地に向かう途中、サファイアの採掘地を通りました。 アンモナイトとサファイアがすぐ近くで採れるというのは、
日本ではちょっと考えられませんね。 このサファイアは、8〜5.5億年前のペグマタイト鉱床起源だそうです。
島の基盤を作る先カンブリア紀の片麻岩にこの時期花崗岩が貫入しました。 このペグマタイトを含む花崗岩
が風化し、古生代の終わりにゴンドワナ大陸分裂に伴い誕生した湖に再堆積した地層からサファイアは発見されています(蟹江2004年による)。
マダガスカルはブラジルやスリランカと並んで、ゴンドワナ大陸を起源とする世界でもっとも有名なペグマタイト鉱物の産地です。
| 注1)ペグマタイト鉱床 | 花崗岩質マグマが冷却される過程で形成される鉱床。 一つ一つの結晶が大きいことが特徴。 |
| 注2)ゴンドワナ大陸 |
|
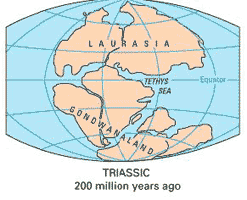 |
三畳紀(2億年前)の世界地図 |
 |
 |
 |
| 化石発掘地から延々歩いてきた半砂漠地帯を望む | 数百メ−トルに渡って続く発掘現場 | 小高い丘の斜面で化石を発掘している |
ゴンドワナ大陸の分裂(ジュラ紀後期)に伴い形成された裂け目に海水が浸入しました。
この地域で発掘される化石は、
このとき堆積した海成層中から発見されます。
 |
 |
ジュラ紀後期(Oxfordian)の化石
(アンモナイト)を含む地層。 |
化石密集層を指し示す筆者 |
 |
 |
|
| 化石密集層の様子 層理面と平行に堆積している多くの二枚貝に混じってアンモナイトも見られる(ペンのところ) 白く見えるのは全部化石 |
アンモナイトの産状の例 層理面と平行に地層中から直接産する |
この地域の地層は西側に緩やかに傾斜しています。 断層は今回の発掘現場内では見られませんでした。
化石はうすいグレイのシルト岩層の下の赤茶色した細粒砂岩層中に密集して産出します。 地層中に直接含まれ、ノジュ−ルを作ることはありません。
シルト岩層からはまったく化石は見つかりません。
ここの化石の特徴はなんと言っても白い殻の残った保存のよさでしょう。 細粒砂岩の地層中から直接産出するにもかかわらず、30cmを超えるアンモナイトでさえも、へその中心まできれいに殻が残っています。 変形もほとんど見られません。 また密集して産出する二枚貝は合弁のものが多いです。 化石と母岩との分離は非常によく、現地で地層から化石だけを堀り出すことも可能です。
2)だれが
この発掘地は1993年に採掘が始まりました。
一人のボスが一つの発掘の穴(縦穴)を所有し、現地の人を3,4人雇って化石を掘らせています。
常時40人ほどの人がこの発掘現場で働いています。 彼らはここでの化石発掘で生活しています。
 |
 |
 |
| 発掘したアンモナイトを見せる作業中の人 | 一人のボスが一つの採掘の穴を持ち 3,4人雇って掘らせている |
この穴では3人が働いていた |
 |
| アンモナイト発掘歴20年のここで 1番の長老。2004年に180kg というこの採掘場で過去最大のアンモナイトを発掘した。 素足で作業している |
3)どうやって
ここでは化石の発掘だけでなく運搬もすべて人の力だけでやっています。 これは発掘の始まったときから変わっていません。
スコップでシルト岩層を2〜4メ−トル(深いところでは6メ−トルも)掘り、その下の硬い砂岩の化石層を鉄の棒だけで崩していくのは
とても大変なことと思います。 化石層にたどり着くまでに、化石のまったく産出しないシルト岩層
を1ヶ月も掘り続けることもあるそうです。
化石層に掘り当たると、うまくいけば一つの縦穴から1日で20〜30kgの化石(アンモナイト、二枚貝、巻貝)が採れるということです。
化石層を掘りつくすとその穴をきれいに埋め戻し、また新たに縦穴を掘り始めます。 彼らは掘っては埋め、また掘っては埋めという作業を延々と繰り返しています。
 |
 |
 |
| 掘り始めたところ スコップで硬い地面を掘り下げていく | うすいグレイのシルト岩層をだいぶ掘り進んだところ 化石はまったく出ない | 3〜4メ−トル掘り下げた もうすぐ化石層に到達しそう |
 |
 |
 |
赤茶色の化石層まで到着すると今度は2メ−トルほどの鉄の棒で化石を含む硬い砂岩層を崩していく |
1日中炎天下で作業している | 発掘に使う道具は、スコップと硬い岩を砕く鉄の棒の2つだけ |
4)何が掘れるのか
ここのジュラ紀後期(Oxfordian)の地層は、保存のよい化石、特にペリスフィンクテス(Perisphinctes )などのアンモナイトが多く産出することで有名です。
ペリスフィンクテス(Perisphinctes)には、30cmを超える大きくなるタイプと、最大でも10cmを少し超えるぐらいでコンストリクション(くびれ)が発達し、
ラペットを持つ小さなタイプの2種類が見られました。
他のアンモナイトとしては、リトセラス(Lytoceras
),ホルコフィロセラス(Holcophylloceras),ユ−アスピドセラス(Euaspidoceras)などがあります。
ほかには
二枚貝、巻貝も産し、ここで産出する化石の中では二枚貝が一番多く見られました。
この発掘地の化石の保存状態でおもしろいと思ったことは、地表から深く掘り下げたところほどアンモナイトなどの殻がきれいに残っている
ということです。
場所によっては化石層が地表に直接露出している所もあります。 そのような場所では化石層の上にあるシルト岩層を掘る手間はかからない
のですか、アンモナイトなどの殻は赤茶色に変色したものが多く、ここの特徴である白いきれいな殻の残ったアンモナイトは
あまり見られませんでした。
これはおそらく透水性の低いシルト岩層が地表からの雨水の浸入を防いでいるのでないか
と考えられます。
化石を多く含む砂岩層は水分を含みやすく、殻を溶かしたり変色させたりしやすいのでしょう。
この地域では乾期は非常に乾燥していますが、11月からの雨期には雨が降ります。
化石発掘人たちがわざわざ苦労して深い縦穴を掘るのは、白い殻の残ったきれいなアンモナイトを発掘するためです。
| 注3) | 小さいタイプのペリスフィンクテスはPerisphinctes(Dichotomosphinctes)、大きくなるタイプはPerisphinctes(Perisphinctes) とされています。 Dichotomosphinctes はPerisphinctes のSubgenus(亜属)です。 この2つのタイプは、ミクロコンクとマクロコンクの関係も考えられます。 |
 |
 |
 |
大きくなるタイプのPerisphinctes (P.) |
30cmを超える大きなPerisphinctes(P.) さすがにこれは担げなかったのか自転車の荷台にくくりつけて運んできた |
左のPerisphinctes(P.) の拡大 住房部に大きな突起が見られる |
 |
 |
 |
| 自分で掘りだしたPerisphinctesを 見せてくれる現地の人 | 1日の発掘でこれだけ採れた | 掘りたてホヤホヤのアンモナイト 母岩がまだ付いている |
 |
 |
 |
1.リトセラス(Lytoceras) |
Perisphinctes(P.)の未成年殻と思われるもの(上の標本)と、コンストリクション(くびれ)の発達する小さいタイプのペリスフィンクテス これらの標本は深い穴底から掘り出されたため、 白い陶器質の非常にきれいな殻が残っている |
|
おわりに
今回は
トゥリアルのジュラ紀のアンモナイト発掘地に行きました。 この次はマダガスカル・アンモナイトの本命マハジャンガの白亜紀前期(Albian)の発掘地を訪れる予定です。
マハジャンガは今回のトゥリアルよりもはるかにアクセスが大変なようで、現地の人もあまり行きたがりません。
聞くところによると一番近い集落(ここへたどり着くのも相当大変)からジャングル地帯を丸一日歩くそうです。
ここでは縦穴を掘り下げていくにしたがって、パ−ルの殻の残ったアンモ→赤い殻のアンモ→グリ−ンの殻のアンモと
産出するアンモナイトの殻が変化していくという話です。 本当にそのような変化が起こるのか、もし起こるとしたら岩相の変化と何か関係があるのか
この目で見てこようと思います。
その時がくるまでしっかりと気力と体力(あとお金)を蓄えておこうと思いました。
今回マダガスカルのアンモナイト発掘地を訪ねてみて、彼ら発掘人たちは炎天下、生活のためとはいえ、毎日このような過酷な労働を10年以上続けているのはほんとうに大変なことと最初は思いました。 人力だけで硬い地盤を掘り、深い穴の底から化石を発掘するのは、重労働なだけでなく、労働基準法も満足にないであろう彼らには、落石や穴の側面が崩れてケガをする危険もあると聞きます。
しかし彼らは、ニコニコと実にうれしそうな顔をして私に掘った化石を見せてくれました。 これは単に仕事というだけでなく、化石に興味を持つ人たちに共通する感情が根底に流れていると私には思えるようになりました。
つまり、朝起きてきょうはなにが掘れるかと勝手に思いをめぐらしてワクワクし、発掘中アンモナイトが地層から少し顔をのぞかせるとドキドキし、そしてその化石を自分の手で苦労して掘り出した時の”ヤッタ”という達成感、そのような気持ちが彼らを動かしているのではないかと思いました。 その気持ちは何も彼らだけのものではなく、私たち化石に興味を持つ人たちにみな共通する感情の一つなのでしょう。
最後に、今年1月に亡くなった早川浩司氏のご冥福をこの場を借りてお祈りいたします。
彼は今回私が訪れたトゥリアル近郊を調査しています。
今回の発掘地から50km南のOnilahy river 沿いのTongobory(北海道産のアンモナイトの名前でもお馴染み)
と支流のSakondry(Calycoceras産出)及び南のRanohandatsa(ラノンダ ジュラ紀から白亜紀後期にかけての地層と化石)には彼の足跡が残されています。
2005年11月
Copyright 2005 Izu Ammonite Museum All Rights Reserved